「藍を継ぐ海」を読み終えた。
.
.
本屋でぷらっと出会った本。この人は初めてだった。
.
.
■
.
.
立派な人だと素直に思う。ここでの暮らしにちゃんと価値を見出し、仕事もプライベートも充実させようと懸命に生きている。地元の人たちにも溶け込んで、地域の産業に貢献までしている。それなのに、あるいはだからこそ、ひどく苦手に感じてしまう。あの自信に満ちた声と目が会社員時代の上司を思い起こさせるからかもしれない。
.
.
「ニホンオオカミには、自分の縄張りに侵入してきたものを追跡して監視する習性があったと言われてましてね。「送り狼」という言葉もそこから生まれたんですよ。今使われているような意味とは本来は違うんです」
.
.
たとえ意欲を持って何かに取り組んだとしても、三年ほどで異動になれば、その先を見届けることはない。逆に、いい加減に働いても、部署が変わればあとのことは知らぬふりができる。異動が多いのは管理職も同じだ。上司が変われば以前の指示が反故にされたり、業務の優先順位が変わったりするのもよくあること。だから余計なことはしない。考えない。今いる住宅係を含め、これまで四つの部署を経験してきた小寺が学んだ役人としての処世術はそれに尽きる。
.
.
「美唄市の前身、沼貝町に当時あった光珠内郵便局。隕石には、発見地点の最寄りの郵便局の名前が付けられるのよ」
.
.
現在、放流会は子ガメが生き残る確率を著しく低下させると考えられている。孵化して地上に脱出した子ガメは「フレンジー」と呼ばれる興奮状態にある。懸命に手脚を動かして大急ぎで海に向かい、安全な流れ藻までたどり着こうとするのだ。
.
.
放流会の多くが日中に開かれているのも問題だという。子ガメは普通、捕食される危険を避けて夜のうちに地上に出てくる。それを人間の都合で明るい時間帯に行えば、当然捕食者から見つかりやすくなる。自然保護とは正反対といっていいようなイベントなのだ。
.
.
以上引用です
.
.
■
.
.
てっきり長編かと読み進めると、それぞれ50ページほどの短編集だった。よく見ると帯の裏にもしっかりと「全5編」と。えー(笑)
.
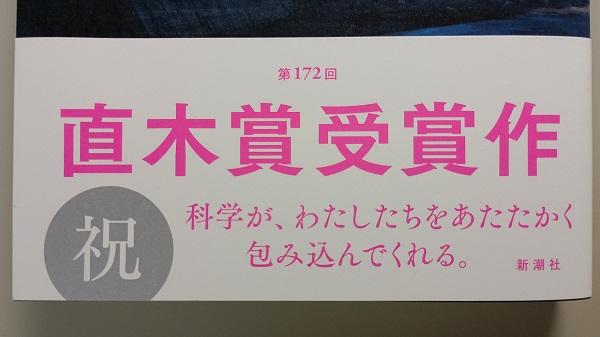
.
どれもサイエンスと動物が絡む物語で、知的好奇心がくすぐられた。
.
中でも狼犬ダイアりー、星隕つ駅逓、そして最後の「藍を継ぐ海」が好きだったな。小説は専ら長編派だけれど、短編も面白いね。
.
不倫、セックス、殺人、LGBTQなど安易に感情を掻き立てられる内容で勝負していないのもよかったです。
.
.
.
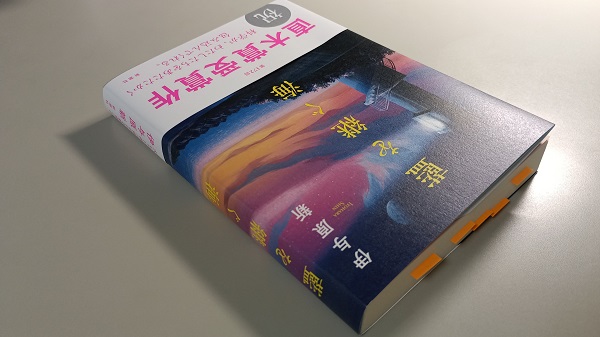




コメント