「ヒルビリー・エレジー」を読み終えた。
.
.
現アメリカ副大統領、トランプの側近であるJ・D・ヴァンスの回顧録、自叙伝だ。
.
.
■
.
.
ほかのほとんどの民族集団がその伝統を完全に放棄してしまったのに対して、スコッツ・アイリッシュは家族構成から、宗教、政治、社会生活にいたるまで、昔のままの姿を保っている。
.
.
私は実際に多くのウェルフェア・クイーン(公的扶助を受けながら怠惰な生活を送る人)を知っている。隣人にも何人かいるが全員が白人だ。
.
.
父の家では、エリック・クラプトンを聴くことはできなかった。歌詞が適切でないといったレベルではない。エリック・クラプトンは悪魔に取りつかれているというのだ。進化論とビッグバン理論は理解すべき説ではなく、対決でべきイデオロギーとなった。
.
.
祖父は間違った時代と場所に生まれてきた、恐るべきヒルビリーだった。
.
.
ヒルビリーは人生の早い段階から、自分たちに都合の悪い事実を避けることによって、あるいは自分たちに好都合な事実が存在するかのように振る舞うことによって不都合な真実に対処する方法を学ぶ。
.
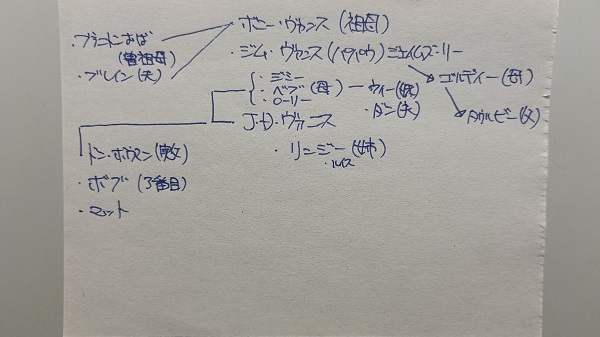
.
本来なら仕事をしていなければならない年齢なのに働かない。仕事に就くこともあるが長くは続かない。遅刻したり商品を盗んでeBayで売り飛ばしたり、息がアルコール臭いと客からクレームをつけられたり、勤務時間中に30分のトイレ休憩を5回もとったりしてクビになる。一生懸命働くことの大切さは口にするのに、実際には仕事に就かず、それをフェアではないと考える何かのせいにする。
.
.
私たちはみんな、なんとか生きていこうと四苦八苦しながら、きちんとやりくりをし一生懸命働いてよりよい生活を送りたいと願っている。ところが、かなりの数の連中が失業手当で生活しそれに満足している。民主党の政策はさほど褒められたものでもないとこのころから思うようになった。
.
.
能力は関係ないと言いたいわけではない。もちろんあるにこしたことはない。ただ、自分を過小評価していたと気付くことと、努力不足と能力不足とを取り違えていたと気付くこと。それにはとても大きな意味がある。
.
.
祖母の心の中にはいつもふたつの神が存在した。イエス・キリストとアメリカ合衆国である。私だけではなく、周りの誰にとってもそれは同じだった。
.
.
私の地元の知り合いたちも、主要なメディアがオバマについてどのような報道をしているかよく知っている。ただ、彼らはそれを信じないのである。アメリカの有権者のうち、メディアが「とても信頼できる」と考えているのは全体の6%にすぎない。多くの国民は、アメリカ民主主義の砦であるはずの報道の自由を戯言にすぎないと考えている。
.
.
私たちのコミュニティの3分の1の人が、明確な証拠があるにもかかわらず大統領の出自を疑っているとするならば、ほかの陰謀説も思ったより浸透している可能性が高いだろう。これは自由至上主義のリバタリアンが政府の方針に疑問を投げかけるというような、健全な民主主義のプロセスとは違い、社会制度にそのものに対する根強い不信感である。しかも、この不信感は、社会のなかでだんだんと勢いづいているのだ。
.
.
イェールに来て、私は生まれて初めてほかの人が私の人生に興味を持っていることに気付いた。私にとっては何の面白味もない出来事、たとえば、さえない公立高校に通っていたことや、両親が大学を卒業していないこと、オハイオ州出身であることに教授やクラスメートは本気で興味を示した。
.
.
テーブルの上に、ばかげた数のナイフやフォークが置いてあるのが目に入った。全部で9本もある。なぜだろう。スプーンが3本もいるのだろうか。バターナイフがいつくもあるのはなぜか。
.
.
ACE Adverse Childhood Experience(逆境的児童期体験) 子どもの頃のトラウマ体験のこと。その影響は大人になってからも続く。
.
.
私の母はパートナーを次から次へと替えていた。このような例は、アメリカ以外の国ではあまり見られない。フランスでは母のパートナーが2回以上変わるのを経験した子どもは0.5%、つまり200人に1人であり、世界2位のスウェーデンでは2.6%、つまり約40人に1人だ。ところがアメリカでは驚くべきことに8.2%、つまり約12人に1人の子どもが母親の再婚を経験している。しかも、労働者階層の場合はこの数値がさらに高くなる。
.
.
なぜ人生を変えることができたのかと彼女に尋ねれば、安定した家庭が将来をコントロールできる自信とやる気を与えてくれたからだと答えるだろう。そして、広い世界を知ることは将来の目標を見つける力になるとも教えてくれるはずだ。
.
.
住民がみんな低所得層だとしたら、その地域には活気も資金もありません。住民が同質ならいい、ということにはならないのです。その地域は絶望の大きな吹きだまりになるからです。低所得層の子どもを、別の階層の子どもたちと一緒にできれば、向上心を芽生えさせられます。
.
.
周囲の大人が「努力しても無駄」と思い込んでいる場所で育った子どもが、希望を抱けるはずがないし努力の仕方を学ぶこともできない。ヴァンスのように幸運でなかった者は「努力はしないが、ばかにはされたくない」という歪んだプライドを、無教養と貧困とともに親から受け継ぐ。
.
.
以上引用です
.
.
■
.
.
ヒルビリーとはなんぞや?
.
ヒルビリーとは田舎者の蔑称で、特にアイルランドのアルスター地方から、おもにアパラチア山脈周辺のケンタッキー州やウエスト・ヴァージニア州に住み着いた「スコッツ・アイリッシュ」のことだ。
.
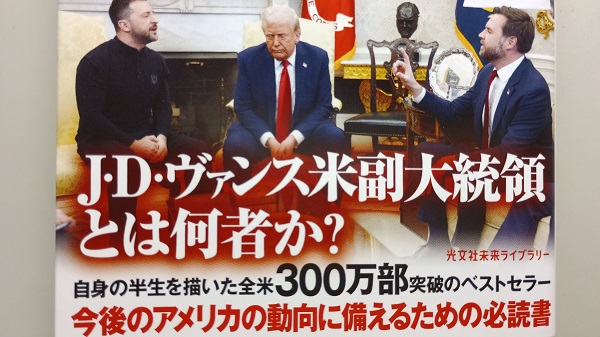
.
アメリカ社会ではレッドネック(首筋が赤く日焼けした白人労働者)やホワイト・トラッシュ(白いゴミ)とも呼ばれている。
.
地理的にはラストベルト、そしてバイブルベルトとも重複するかなり保守的なエリアになる。
.
■
.
いわゆる社会の低層で、決して恵まれた環境で無かったにも関わらず、アイビーリーグのロースクールから弁護士へ、そしてバイスプレジデントにまでのし上がったヴァンスの半生だ。
.
読めば実戦での「ヒルビリー」というものがよく分かる。
.
彼の場合は、祖父と祖母、ミドルタウン、海兵隊、イェール大学、ウシャ、福音派が現在のアイデンティティを形作っているんじゃないかな。
.
負の連鎖を断ち切れたのは、生まれもった才能も幾分あるだろう。しかしながらその理由の大部分は運だと思う。
.
信頼できる家族とお手本となる人物に巡り合えなければ、そもそも努力しようとすら思わない。
.
こちらはフィクションだけれど「百年の孤独」にも似ていた。
.

.
それだけ壮絶な人生ということだ。
.
■
.
共和党が難色を示しているアファーマティブ・アクション、その他の公的制度でイェールに入学できたのなら、その分くらいは社会へ還元してもいいのでは。そんな風にも感じたな。
.
.
最後に印象に残ったところを。
.
私が卒業した高校からは、なぜアイビーリーグの大学に進学する生徒がひとりもいないのか。アメリカのエリート教育機関にはなぜ、私のような学生がほとんどいないのか。私が育ったのと同じような境遇の家庭はなぜ、これほど多くの問題を抱えているのか。私はなぜ、イェールやハーバードには手が届かないと思ったのか。そして何より、成功した人たちはなぜ、こうも私とちがうのだろうか。
.

.
アメリカの政策の背景がすこーし理解できると思います。
.
.
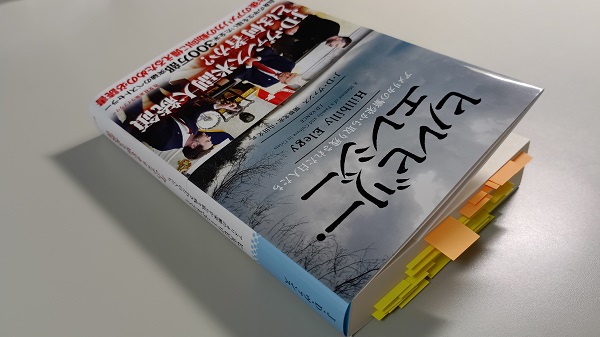




コメント