「THIRD MILLENNIUM THINKING アメリカ最高峰大学の人気講義」を読み終えた。
.
.
本屋でぷらっとな。たぶん面白いので購入。
.
.
■
.
.
当然ながら、3千年紀における変化は悪いことばかりではない。というより、悪い部分はほとんどない。自律した思想家たちの世界は、信者ばかりの世界よりはるかに素敵に思える。しかしながら「国内や世界で繰り広げられるている対話が、特定の人向けのニュースやソーシャルメディアのエコーチェンバー現象によって切り取られ、分断される」「驚異的な勢いで謝情報や偽情報が拡散され、判断に偏りが生じる」といった問題が起きれば、そのたびに対処しなければならない。
.
.
[エピストクラシー] 一定の学歴、つまりは一定の知識がない人には投票を一切行わせない考え方。
.
.
意思決定における自律性が過度に重視されるとどうなるか?選択の自由をあきらめて専門家の言うとおりにするか、それとも専門家の意見と呼ばれるものは却下して自分の自由を守り「独自に調べる」か。後者を選べば、ユーチューブの視聴に200時間を費やしたり、自分にとって正しいと思えることに取り組んだりすることになるだろう。人は様々なバイアスを抱えていて、たとえば、強いカリスマ性を感じさせる人が発する言葉を真に受けやすい。また、自分のなかに根付いている偏見を肯定をするストーリーを信じる傾向や好ましくないと思う人と悪者扱いする傾向もある。
.
.
二酸化炭素の濃度によって認知テストの結果がどう変わるかを調べた結果がある。それによると、濃度が800以下でテストを受けた人々の成績がいちばんよく、濃度が1000前後で受けた人々が彼らに続いた。濃度が1200で受けた人々の結果はかなり悪く、この濃度は、大学によく見受けられる歓喜システムの整っていない講義室で1時間の授業が終盤に差し掛かったときの濃度に近い。
.
.
[トライアンギュレーション] 複数のエビデンスを使ってひとつの事象の信頼性を高めること。
.
.
[Spurious Correlations 見せかけの相関関係] 一例を紹介すると、2000年から2009年にかけてアメリカでは一人あたりのチーズの消費量が着実に増加するなら、ベッドのシーツに絡まって亡くなる人も同様に増加した。
.
.
法学者であるサー・ウイリアム・ブラックストーンが「ひとりの無実の人に有罪を宣告するくらいなら、10人の罪を犯した人を無罪にするほうがいい」と論じたのは有名な話だ。要は、無実の人に有罪を宣告すれば、真犯人を野放しにすることにもなるのだ。よって、有罪判決に対する先入観は持っていたほうがいいということになる。
.
.
白い白鳥を何羽見ようとも、すべての白鳥が白であるという推論を容認することはできないが、黒い白鳥が1羽観測されるだけで、その推論の反証として十分である(ジョン・スチュアート・ミル)
.
.
偽陽性率が高くても、そうした希少疾患かどうかの検査をすれば、本当にその病を患っていたときに必要な治療を受けられるのだから検査を受ける価値はある。偽陽性だと判明すれば、その不安を長く放っておくことはないし、不必要な治療を受けることもない。陽性となればたいてい、もう一度検査を受けることになる。その検査は最初のものより高価だが、偽陽性のエラーが出る確率は低い。より高価な検査は、誤って陽性と判明した多くの人に正しい結果を伝えるために活用されればいい。
.
.
科学は確率を推定する方法を教えることはできても、決断を下すために使うべき基準がどれかを教えることはできない。決断の基準となるい自分にとっての「証明度」は価値判断を表すものだ。
.

.
選挙の投票用紙に候補者の氏名が列記されていて、ほかの条件がすべて同じである場合、最初に書いてある候補者に投票する人の数がわずかに多い。最初に氏名が記された候補者は残りの候補者より約5%多く票を勝ち取る。その影響は本当に大きいい。意外に思うかもしれないが、同じことを視覚的にではなく口頭で行うと正反対の影響が生まれる。
.
.
[p値ハッキング] 自分の求める結果を得るまでさまざまな分析を確かめる行為
.
.
人はときとして、意見の真偽に対する自分の本心(死刑や銃規制は殺人の減少に効果的であるという意見に賛成/反対)ではなく、自分の価値観(自分は保守/リベラルである)を誇示したい欲求に突き動かされた行動をとる。
.
.
人はデータを改ざんするときに、虚偽のランダムノイズをデータに混ぜ込むのはあまり上手でないことが分かってきた。虚偽のデータをグラフにすると完璧なベルカーブを描き、その測定に見受けられて当然の、統計的不確かさ以外のノイズが一切含まれていない。
.
.
実際のところ、妥当な答えを得られている限りは、信頼できないデータを見つけて排除したり、ソフトウェアのバグを見つけて修正したりしないことが当たり前になっている、つまり予期せぬ結果が出れば問題のあるデータやバグを探すが、結果が正常に見えれば探そうとしないのだ。
.
.
人は物語の結末を先に知ると、物語を生み出す人になったつもりでその結末に即して解釈しようとする。結果が分かっていると、結果の質に即して決断の質を評価しようとするバイアスが働く。
.
.
[レジスタード・レポート] 研究者が実施予定の研究の詳細を学術誌に提出し、その研究が理論的に正しく、研究方法が査読を通過すれば、研究に着手する前の段階でその研究論文の掲載を学術誌が保証すること。期待外れの結果に終わった研究の論文は掲載される確率が低いという確証バイアスの軽減と、興味深い仮設を実証する結果だけを掲載し、仮設を検証する結果はリジェクトするという学術誌の偏りを是正する。
.
.
[集団浅慮] 結束力の強い内集団のなかで全員一致を希求する機運が高まり、現実に即した代替策の評価を顧みなくなった人々が陥る状態を素早く簡潔に表す用語。
.
.
ジャニスは集団浅慮の主な兆候として、次の8つをあげた。「不死身の幻想」「集団固有の道徳観の信仰」「集団の正当化」「外集団に対するイメージの固定化」「自己検閲」「全員一致の思想」「反対者への直接的な圧力」「自薦の用心棒(異論にさらされることから集団のリーダーを守る存在)」だ。もうひとつの危険因子は「不健全な組織文化」でこれは、外部の声の遮断、公平なリーダーシップの欠如、メンバーの社会的バックグラウンドやイデオロギーにおける多様性の欠如から生じる。
.
.
一般的な集合知のメカニズムでは、参加者にいい結果を出したいという欲求はあっても、正確さを求める動機はない。一方、予測市場の参加すると口先だけでなく行動を起こすことになる。というのは、1998年のアメリカ国政選挙において、予測市場が世論調査を専門に行う会社の予測に勝ったのだ。予測市場は世論調査(個別の調査結果に含まれるエラーが相殺されるぶん、正確さが高い調査)の平均より優れた結果を出すことが多いと判明した。
.
.
関心経済(アテンション・エコノミー)ならぬ、信頼経済(トラスト・エコノミー)の実践を真剣に考えることだ。その実践という名の新たな実験を通じて、他者の意見に寛容な思考が報われる新たな方法を模索するのだ。
.
.
その実験には「質の高い調査報道を支援する新しいメカニズムを構築する」といったことも含まれる。例えば、インターネット上の記事を読んだ読者が、その記事を書いたジャーナリストにごく少額を支払えるようにする技術を開発しようという議論は随分前から起こっている。それはひとえに優れた仕事に相応の対価が支払われるようにするためだ。
.
.
科学者でない人にも科学的楽観主義は必要だ(科学的楽観主義の正反対と呼ばれる現象が学習性無力感だ。人間をはじめとする様々な動物は、自分の力が及ばないという状況を繰り返し体験すると、そういう不快でつらい状況を変えることをあきらめてしまう。実際に改善することができる状況でも、改善を試みることすらしなくなってしまう)
.
.
以上引用です
.
.
■
.
.
ノーベル物理学賞を受賞した学者、哲学者、そして社会心理学者の3者の共著。錚々たる大学の錚々たるメンバーだ。
.
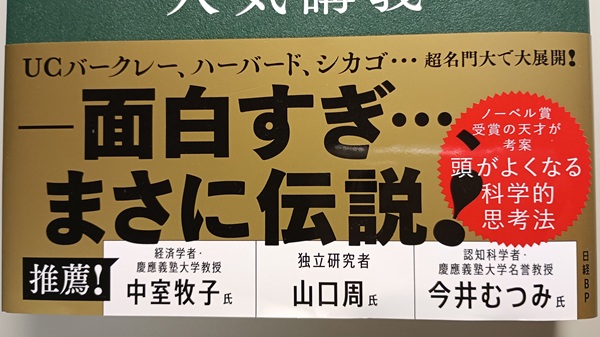
.
複雑でますます不確定要素が増す世の中を、うまく選択し泳いでいくコツを教えてくれる。
.
行動経済学と統計学の見地が多い印象だった。科学の分野で培われてきた手法を、身近なライフハックめいたものに転用するみたいな。
.
印象的だったのは
.
.
根拠を手に入れたところで絶対的な確実性はたいてい得られないのだから、完璧な答えを求めるより「自信の度合いにもいろいろある」という概念を理解するほうがよほど役に立つ。
.
.
これを蓋然的思考という。うまい折衷案みたいなものだろうか。
.
その思考のエラーを防ぐ方法のひとつとしてダブルブラインドテストが挙げられている。科学系の本には頻出する単語で、バイアスゼロの「自分自身を知らない状態に落とし込む」方法だ。
.
すべてに白黒つける「0、100思考」は痛快だ。でも現実の社会は複雑系で、参加者全員がハッピーになる処方箋などない。
.
さらに言えば、そういう思考が身につくほど常にイライラし健康にもよろしくないかと。
.
■
.
人間はすぐに間違える。
.
それは著名な専門家でも同じ。
.
そして個人でも集団でも。
.
しかしながら、
.
事実 ⇔ 越えられない壁 ⇔ 価値観
.
この大きな壁の向こう側を自在に往来できるヒントになると思う。あとは楽観的科学主義を忘れずに。
.



.
情報の取り込みすぎもよろしくない。暇なら無理にスマホを弄らず、ボーッとしてりゃいいんだよ(笑)
.
ちなみに政治学者のロバート・アクセルロッドの TFT(tit for tat)戦略は日常生活にも使える。以前橘玲氏の本で目にしたことがあり、特におとなしく性格の暗い人間には非常に有効だと思う。
.
シグナルとノイズの件は、古い本だけれど「シグナル&ノイズ 天才データアナリストの「予測学」」が最高に面白いです。
.
.
.
.
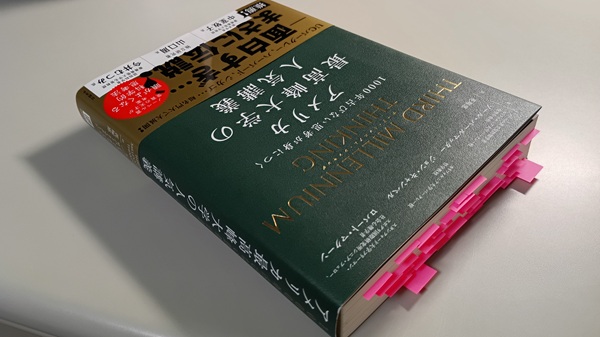




コメント