「ユダヤ人の歴史 古代の興亡から離散、ホロコースト、シオニズムまで」を読み終えた。
.
.
面白そうだったので購入。この人の本は初めて。
.
.
■
.
.
ユダヤ教、キリスト教、イスラムに共通する信仰は「排他的一神教」と呼ばれる。自分ないし、自民族が信仰している神は、他者、他民族も支配しており別の神を崇めるものは、単にそのことに気づいていないだけということになる。三宗教とも、世界を唯一司るところの同じ神を信仰することは相互に了解している。異なるのは神の道に到達するための考え方や実践である。
.
.
反ユダヤ主義は、反ユダヤ的なキリスト教徒とユダヤ人が対峙する単純な構図から生まれ暴力に発展するのではない。ユダヤ人を金づるとして利用する権力者と、それを腐敗と捉える庶民の間にユダヤ人が挟まれるという三者関係こそが、一定期間秩序を維持しながらも庶民の反ユダヤ感情を蓄積していく。政変や不況などでこのタガが外れたとき、民衆の怨念は一気にユダヤ人に向かう。
.
.
経済が好調であるときはその潤滑剤となり、直接的な利益を得る身分や階層からは重宝され保護されるが、不況になりその保護が行き届かなくなると下層からの怨念を真っ先に浴びることになりがちなのがこの中間マイノリティだ。単なる上下関係ではなく、まさに三者関係という組み合わせのなかでその運命が左右されるのがポイントだ。
.
.
[スファラディーム] ユダヤ人の二大系統の一つ。スペイン系ユダヤ人のこと。
.
.
[アシュケナジーム] ユダヤ人の二大系統のもう一つ。ドイツ系ユダヤ人のこと。
.
.
今日でも、とくにイスラエルでは黒服のユダヤ人(超正統派)は、政府から補助金や税金の免除を受けることができ、働かずに一日中ユダヤ教の勉学に励んでいる。そのかわり、妻が外で働く。
.
.
「同化」は人間関係や婚姻関係、アイデンティティなどにおいて周囲の社会と一体化する傾向が強い状態を指す。他方「文化変容」は言語や社会習慣の点においては周囲の社会に適応しているものの、自己意識や社会関係の点では変容前の集団とのつながりが維持されている状態を指す。
.
.
[ポグロム] 雷や轟音を意味する「グロム」を語幹に据えるロシア語。民衆間の集団暴力のことで、おもにユダヤ人に対して用いられてきた。
.
.
ロシアのシオニストにとって、必ずしもパレスチナに行かないシオニズムにはどういう意味があったのか。それはロシア帝国において差別されていたユダヤ人を誇り高き民族に引き上げるためのアピールだった。いつもユダヤ人ばかりがポグロムの対象になるのはユダヤ人が国を持たずに放浪したり、農民に寄生したりする賎民だと蔑まれているからだとシオニストは考えた。
.
.
現在の科学の基準では「人種」という概念はあまりに杜撰であるため、使用されることはない。肌の色や体格、顔つきといった外見的特徴を恣意的に分類し、それと中身を結びつける発想には無理があった。肌の色一つとっても、境界はグラデーションなので線引きは恣意的になる。肌の色にかかわらず血液型が同じであれば輸血可能だが、似た色同士でも血液型が異なれば不可能だ。肌の色は生物学的には文字通り表層にすぎない。それが社会学的な意味を持ってしまったのが人種主義の歴史である。
.

.
ポーランド民族主義者の観点では、少数民族は国民統合にとっての障害にとどまらなかった。国境の向こう側のそれぞれの「同胞」とのつながりが懸念される安全保障上のリスク要因でもあったのだ。つまり、ユダヤ人は人種として劣っていてポーランド人を遺伝的に蝕むから排除するという人種衛生学的な動機があったわけではない。ユダヤ人を単体として危険視したのではなく、危険な敵と手を結ぶスパイないしその予備軍のようなものとして過大評価したのである。
.
.
収容されたユダヤ人はしばしば東方での労働にも充てられ、過酷な環境ゆえに死者も多くでていわば淘汰された状態だった。ところがヴァンゼーで行われた会議では、この生存者こそが頑強なユダヤ人の核であって、ユダヤ的生活を再建する危険分子だとされる意見が出された。彼らこそ殲滅しなければならないと。
.

.
ユダヤ人差別というと、ユダヤ人を蔑む方向性にばかり注目が集まりがちだが、差別とは必ずしも蔑むことだけを意味するのではない。あるカテゴリの人々が一様に同じ性質を持つことを、当事者一人ひとりの固有性を無視して決めつけることに差別の基礎がある。そこの蔑みを込めれば典型的な差別となる。しかし、褒めたつもりでも社会の中で選択肢が限られた者に対し、特定の役割に押し込める方向で勝手な決めつけを行うのであれば、典型的な差別と本質は変わらないことになる。例えば、ある人が女性というだけで子育てに長けているとか料理がうまいと決めつけることが差別とみなされるのはこのためである。
.
.
イギリスはオスマン帝国との戦いを優位に進めるために、1915年にメッカの太守との間でフサイン・マクマホン協定を結んでオスマン帝国のアラブ地域の独立を支援する約束をした。ところが、ユダヤ人からも協力を引き出すため1917年にバルフォア宣言を発し、パレスチナにユダヤ人の民族的故郷(国家とは言ってない)を作ることも支持したのである。
.
.
さらにイギリスはオスマン帝国解体後の勢力圏をフランスやロシアと山分けすべくサイクス・ピコ協定を1916年に締結した。パレスチナや現在のヨルダンやイラクではイギリスが、シリアやレバノンではフランスが優越することが確認された。現在のトルコ東部を約束されたロシアは革命後に離脱しこの秘密協定を暴露した。以上はイギリスの三枚舌外交と呼ばれる。
.
.
イギリスが対応しきれなくなるとパレスチナの問題は国連の場で協議されるようになり、1947年にパレスチナ分割決議が採択される。だが、パレスチナの人口の3割しか占めなかったユダヤ人に6割近くの面積の土地を与えるこの決議に対してシオニストは賛成した一方でアラブ諸国は猛反発した。
.
.
1948年5月、イギリス統治委任の終了に合わせてベングリオンがイスラエルの独立を宣言すると、翌日からアラブ諸国とのあいだで第一次中東戦争が開始された。士気が高かったシオニスト軍は大勝し、翌年に分割決議以上にユダヤ領が増える形で停戦となった。この停戦ライインを「グリーンライン」と呼び二国家解決が謳われる際に想定される国境線となった。
.
.
現在のイスラエルではアラブ人、アラブ諸国からの攻撃や非難をおしなべてホロコーストのアナロジーで理解する傾向がある。ポグロムのアナロジーで現実を捉えてしまうのと同様の事態だ。この結果、シオニストの加害行為への応報さえも不当な被害として理解する思考が常態化してしまっている。
.
.
[宗教シオニズム] ユダヤ教によってシオニズムを正当化する思想。ユダヤ教からは、ユダヤ人がパレスチナを排他的に共有しなければならないとの教義は生まれないはずだが、現在の宗教シオニストはイスラエルの政権にも参画しながらパレスチナ人の追放を公言してはばからない。
.
.
2024年現在、イスラエルのユダヤ人口700万人に拮抗する600万人程度のユダヤ人口を擁するアメリカは最大のイスラエル支援国となっている。だが双方のユダヤ人には微妙な緊張関係もある。イスラエル・ユダヤ人からすれば、本来イスラエルに「帰還」すべきところ異郷にとどまるアメリカ・ユダヤ人は十全なユダヤ人になることができていない。他方、アメリカ・ユダヤ人は、自らマイノリティの条件下で努力してユダヤ人であり続けているので、何もしなくてもユダヤ人の地位に甘んじられるイスラエルの同胞とは一味違う。しかも自分たちはイスラエルを支援していやっているのだ。
.
.
2020年のピュー・リサーチ・センターの調査によるとアメリカ・ユダヤ人のうち、改革派が37%、保守派が17%、正統派が9%、その他が4%で残りの32%は特定の派に属さないと答えている。こうした多様化はユダヤ人内部でも様々なあり方が許容されるようになったことの裏返しでもある。
.
.
以上引用です
.
.
■
.
.
古代から近代、現代史へと続く3,000年に渡る壮大なユダヤ史。
.
ニュースで流れる上澄みだけで知った気になるのは悲しいので、一度しっかり読んでみたいと思っていた。
.
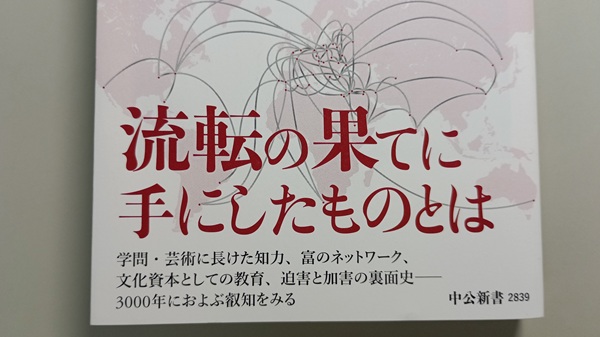
.
到底新書一冊読んだくらいでは複雑すぎて分からないけれど、ぼんやりとしたユダヤの原型みたいなものは見えてくるかも。
.
■
.
特に紀元前からの従属の歴史の中で、現代まで途切れることなく生き残ってきた変遷が興味深い。
.
自分がユダヤ人と聞いてぱっと思い付くのは、ヴェニスの商人のがめつい人、故郷を追われたかわいそうな人、そして影の支配者?(笑)
.
ユダヤ人は決して力や権力があったわけではないんだけれど、まるで遺伝子が都合よく人間を乗り換えていくように、変化への対応力が極めて優れていると感じた。
.
古くはペルシア帝国支配化で「秩序を乱さなければ、自らの宗教の自治は守られる」ことを学び、周囲との差異が目立つ状況で自集団を維持する方法を習得。
.
孤立すると先細りしかねず、周囲に合わせぎると同化して消えてしまうかもしれない。
.
この塩梅を数千年前からすでに探っていた。
.
つまるところ、にわか移民とは違うプロのディアスポラなのだ。
.
強いだけでは生き残れないのは歴史が証明しているよね。
.
■
.
そしてもう一つはユダヤ教の特徴のひとつである「できるだけ議論を積み重ねながら協同で慎重に解釈しドグマ化しない」という姿勢だろう。
.
悲しいかな、控え目に言っても今のイスラエルには当てはまらない。
.
アラブ人とユダヤ人の対立と同様に、ユダヤ人同士、果てにはシオニスト同士でも激しい対立がある。ユダヤ教の中にも細かい宗派が分かれていてそれぞれがそれぞれを主張している。
.

.
最後に印象に残ったところを
.
.
ディアスポラのユダヤ人の歴史は、ユダヤ人が何かを作ったのではなく、ユダヤ人が他のものに作られた歴史である。
.
.
とにかく関係性が複雑怪奇で、ステークホルダーが多すぎる。
.
イスラエルとカナンの解決は、どちらかが全滅するくらいの何かが起きないと無理じゃなかろうか。
.
そんな風にしか思えなかった。
.
.
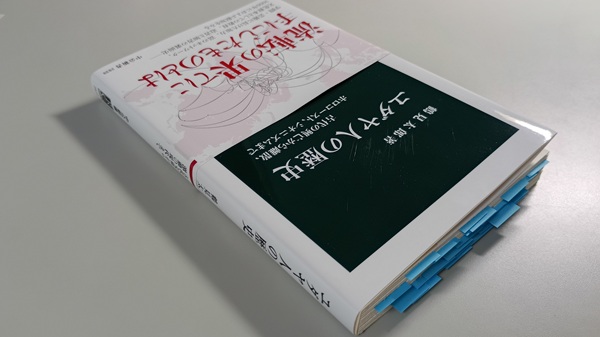




コメント