「STOIC 人生の教科書ストイシズム」を読み終えた。
.
.
著者はストイシズム研究者。この人の本は初めてだった。
.
.
■
.
.
哲学を実践する者が最初に取り組むべきことは何か?それは「自分は知っている」という考えを捨て去ることだ。人は「知っている」と思っている何かについて学ぼうとすることはないからだ。
.
.
わたしの考えや行動が正しくないと誰かに教え諭されたなら喜んで受け入れよう。真実を追い求めて怪我をした人は一人もいないのだから。むしろ怪我をするのは誤ったまま無知のままでいる人たちだ。
.
.
高い倫理規範を掲げることと、自分に厳しくあることは同じではない。前者は自らの言動の改善につながるが、後者は過剰な自己批判を招く。他者を傷付けるようなことは言わないのに、なぜ自分自身を傷つけることは言ってもいいとなるのか。
.
.
他者の好感を得たいという衝動に駆られると、それが強い願望となりひいては不安を招きかねない。くわえて何を行うときの楽しさが半減することになる。というのは、行うことそのものよりうまく行うことに意識が向いてしまうからだ。
.
.
あなたが一番活力に満ちていて、自分自身にもまわりの環境にもしっくりきていたときのことを思い出してほしい。それは何をしていたときだったか?またあなたの内なる炎に火をつける活動を最低3つあげ、今の生活にできるだけ多く組み込むにはどうすればいいか考えてみよう。
.
.
ひとつは、好きで間違う人はいないということ。間違ったことをしている人も自分は正しいことをしていると思っている。そしてもうひとつは他者が何をしようとも自分は自分で満足を見いだせるということだ。
.
.
誰かの恥知らずな行為に腹が立ったときは、直ちに自問せよ。「では、恥知らずな人がこの世からいなくなることはあるか?」と。そんなことはありえない。ならば、ありえないことは求めるな(マルクス・アウレリウス 自省録)
.
.
したいことがあるなら、それをする習慣をつければいい。したくないことがあるなら、それをしないようにし代わりの何かをすることに慣れさせればいい。怒りを感じたときは、悪いことがあなたに降りかかっただけでなく、その感情が生じる習慣が強化されたことになる。いわば火に油を注いだようなものなのだ。
.
.
他者を自分の思い通りにしようとするものではない。いくら力を尽くしたところで、相手の考えや振舞いを支配することはできない。自分の影響力の限界を受け入れることで、自然と調和した生き方によって幸福に至れるという考えを体現できるようになる。
.
.
他者の行動が影響力を持つのは、自分がそうさせているからだちう考え方を受け入れる。他者の行動が明らかに攻撃的だったり不当だったり、あるいは道義に反しているとしても、自分の反応の責任は常に自分で負う。
.
.
人は快楽に身を投じ、それが当たり前になってしまうと快楽なしでは何もできなくなる。これほど悲惨なことはない。かつては不要だったものがなくてはならないものになってしまったのだから。それではもう快楽の奴隷であり快楽を楽しんでいない(セネカ)
.
.
欲に駆られて行動すると、本当の意味での価値がないものを手にする代わりに、本当の意味での価値があるものを失う。それで失うものの大きさを思えば、自分の価値観に則した行動をとっていかないと夜もおちおち眠れなくなる。
.
.
人生は聖人の生き方と世間一般の生き方のちょうどいい中間をとるべきだ。私たちが目標とするストイックな生き方とは「知恵、正義、勇気、節制」とともに生きていけることであり、同じようにしたいと周囲に思わせることだ。聖人のように、それでいて聖人のような人たちだけで孤立せずに生きていくことを目指してほしい。
.
.
以上引用です
.
.
■
.
.
ストイシズムって何なのさ?
.
ストイックの名詞形だろうか。具体的には目的と意志を備えた人生にするための手段で、その達成には文字通り自制と内省が必須になると。
.
哲学者の言葉をもとに、自らの人生をよりよく生きるための指針が90日間のプログラムとして説かれている。
.
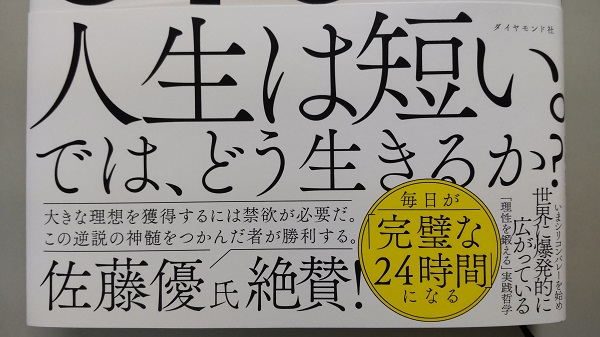
.
仏教や儒教などの教えにも通ずるところがあると思う。
.
つまるところ、足るを知る、他人と過去は変えられない、他人が見てないところでも善行を積む、など大半は内面の磨き方だ。
.
「自己啓発なんて」という見方もある一方で、定期的に読みなおすのは意味のあることだと思っている。どうせすぐ忘れるんだけれど、一時的でも戒め襟を正すことができる。怠惰な人間には反復がかかせない。
.
・・・
・・・
・・・
.
この本をこうして手にして読むだけでも十分ストイックではなかろうか・・・甘すぎ?(笑)
.



.
最後に印象に残ったところを
.
.
あなたのまわりにいるのは人格者ばかりだろうか?人を人格者とみなす決め手となるものは何か?あなたが魅力を感じる振舞いはどういうもので、なぜその種の振舞いに魅力を感じるのか考えてみよう。
.
未来のことに煩わされるな。必要なときがくれば、いまあなたが現在のことに使っているのと同じ理性で対応できるのだから(マルクス・アウレリウス 自省録)
.
.
いい本でした。
.
.
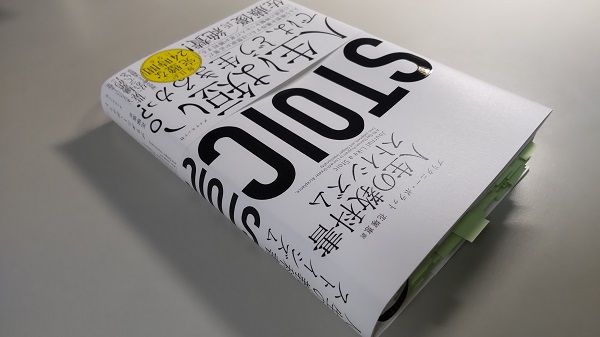




コメント