「人生のレールを外れる衝動のみつけかた」を読み終えた。
.
.
著者は人間、環境学の博士で哲学者だそうだ。なんだか面白そうだったので購入。この方の本は初めてだった。
.
.
■
.
.
寄る辺ない消費者の欲望は、往々にして感情の高揚(欲望の強さ)で勝負しています(最高、尊い、神、クソデカ感情など)しかし、そういう欲望は、実際は色々なものに自分の判断基準を預けることで成立するもの、つまり他者の欲望を自分の欲望としてコピーすることで成立するものなので、内発性(自分の内から湧き出ているという性質)がありません。
.
.
深い欲望は、感情的な刺激を伴わない地味な欲求であり、他人指向型ではなくものすごく個人的な欲求であり、従って表立って見えにくいという性質を持っています。要するに、強さの軸で語られるモチベーションが公共的で抽象的であるのに対して、深さの軸で語られる衝動は個人的で細かく特定されています。
.
.
活用されうるが、普段は働いていない衝動はいつでもそれなりに蓄えられている。そうした衝動が表に出て活用されることを回心と呼び、それが突然やってくるときには再生と呼ぶ。
.
.
「標準的なルート」というまっすぐな道をたどることが、成功するための最も安全なルートだという幻想が作り上げられたしまった。しかし実際のところ、そのルートが安全だと言えるのは、あながた既存の鋳型に自然にフィットするごく少数の幸運な人々のひとりだった場合のみだ。それ以外の場合は、あなたの個性と既存の鋳型のあいだにギャップが発生する。そして、そのギャップにおいて純粋かつ完全なリスクが表出するのだ。
.
.
目の前のものを情報として受け取ることに慣れていると、目の前のものに「誘惑される力」を自分で開発するチャンスが無くなってしまう。誘惑って、実は共犯関係なので対象に魅力があれば自動的に誘惑が生じるわけではないんです。こちらが一定の感度や感性を持っていなければ、魅力に気付くこともできません。
.
.
私たちは色々な人物や出来事から絶えず影響を受けており、その中には善も悪もどちらでもないものも含まれている。善悪の線引きをしようとする意欲を持ちながらも「自分たちはまともだ」「自分は善良だ」と暗に言い聞かせて安心する浅はかさからは距離を取るのが大切です。
.
.
マルチタスキングの常態化は、何事にも没頭せず注意を分散させるための練習を日夜積み重ねるようなものです。何のためにそんな研鑽を積んでいるかというと、マルチタスキングがもたらす注意の分散状態が「快楽的なダルさ」となって、自分の寂しさや、そこからくる不安や退屈を一時的に忘れさせてくれるからです。
.
.
誰でもいい、何でもいいと思ってコミュニケーションや刺激を求めているとき、求めている対象(誰かや何か)が交換可能なだけでなく、求めている自分の側も交換可能な存在になっています。交換可能な存在同志が接続したところでその関係性は持続しません。仮に持続したとしても、妙に依存的でお互いを単純な鋳型に押し込むような関係性になるのがせいぜいのところだと思います。
.
.
以上引用です
.
.
■
.
.
「衝動」という捉えがたい概念を、漫画や小説など様々なジャンルの身近な例を挙げながら紐解いてくれる。丁寧で分かりやすく書かれていた。
.
誰もがひとつくらい知ってる話題があるんじゃないだろうか。自分だったらダニエル・ピンク、クレイトン・クリステンセンあたりだ。
.
もう少し漫画に造詣が深ければさらに深く読めたなーと。ゴルゴなら饒舌なんだけれど(笑)
.
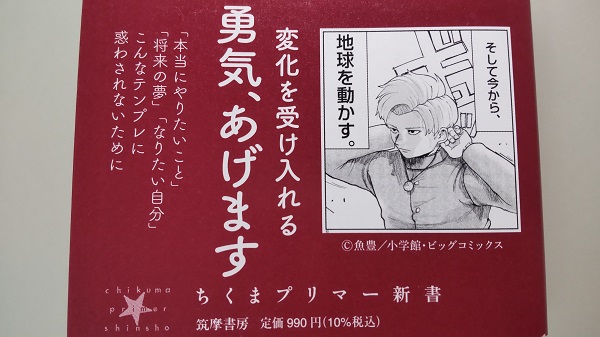
.
衝動とは何だろう?
.
「コントロールできない情熱、過剰なパッション、非合理な欲動、結果自分でも驚いてしまうくらいの行動」みたいな感じらしい。
.
衝動で一番惹かれるのは「打算的ではない非合理さ」だ。自分も20代で人生のレールを外れ(会社員を辞めるという意味で)それからも外れに外れ続けて今に至る。
.
別に何かを成し遂げたいという大志などはなく、やるせなさだったり、反発心だったり、若気の至りなんかもあったかもしれない。
.
そういう意味では、本書で必要とされる「衝動に伴う計画性」は皆無だったな(笑)
.
■
.
思うに、ニヒリズムであれセルフインタビューであれ、まずは自分としっかり向き合うことだろうか。「汝自身を知れ」とはよく言ったもので、本当の自分を理解できなければ、深みにある本心にはたどり着けない。
.
「私には価値があります。こんなにすごい人間です。社交的で人当りがいいんです」なんて価値観だけじゃつまらないよね。
.
あとは好奇心かな。実際に読んでみないと分からないし、観てみないと分からないし、食べてみないと分からない。
.
個人的に、評価社会の欠点と限界は心に留めておいたほうがいいと思う。楽しみを奪われてしまうよ。あまつさえ「楽しみ搾取」だ。
.
そしてノードが増えるにつれ、一見コスパが悪く時間がかかり無駄で関係無さそうなことが偏愛に繋がったりするものだ。
.
無限に流れてくる刹那的なフィードから「他人の衝動」は見えてきても、自分の衝動は永遠に分からない。
.






.
最後に印象に残ったところを
.
.
競技選手の張り詰めた優雅さが見ている群衆にどう伝染するかを知っている人、あるいは植物の手入れに夢中になっている主婦の喜び、その主婦の夫が家の前庭に手入れに対して持つ強い関心、そして、暖炉の中で燃え盛る薪を突き、はぜる炎と崩れゆく炭を見つめる人の熱意に気付き人こそが、人間経験の中にある源泉を知るだろう(ジョン・デューイ)
.
.
そしてこの本「死にがいを求めて生きているの」から
.

.
無人島に行って、やっと、何かを成し遂げた人になれたんでしょうね。人間本来の意味なんて、普通の暮らしの中で見つけられるのに。命の使い方なんて、生きがいなんて、どこにいたって感じられるはずなのに。
.
.
大変面白かったです。いい大人が読んでも楽しかったです。
.
.
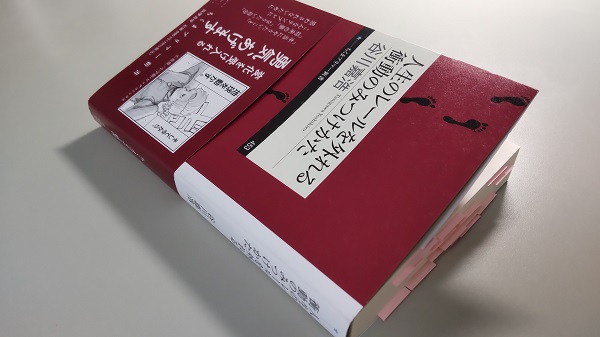




コメント