「酒を主食とする人々」を読み終えた。
.
.
高野秀行さんの新作。
.
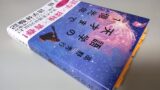
.
大好きで何冊も読んでいる。
.
.
■
.
.
クレイジージャーニーは一度「ヤラセ事件」で打ち切りになっている。TBSは不適切な手法で視聴者の信頼を損なったとして番組を終了させたのだ。
.
.
日本では親が子供の口に食べ物を運んであげる「あーん」を、ここエチオピアでは同じテーブルを囲んだ誰にでも行う。グルシャと呼ばれ、親しみや敬意を表す行為とされている。
.
.
チュチュによれば、コンソ人は一人あたりチャガを朝1~2杯、昼1~2杯、夜3~4杯飲むという。彼の言葉を信じるなら、1日に2.5~5リットルも飲むことになる。
.
.
三女の子は12歳のときから本格的にチャガを飲み始めたという。コンソでは子供は2~4歳で少しずつ慣れさせていき、12、3歳で主食としてチャガを飲むようになるらしい。主食酒開始の時期を決めるのは親である。
.
.
蜂蜜酒とアラーケがある。アラーケとは蒸留酒のことだ。名称自体はイラクのナツメヤシの蒸留酒「アラク」に由来する。酒の蒸留は画期的な技術だったようで、トルコではラク、ブータンではアラと世界各地の蒸留酒の名称として残っている。
.
.
まず、菜の花似のブランゴを混ぜたソルガム粉を発酵させ、その後でそれを別のソルガム粉に混ぜて発酵させ酒にする。あえて日本人的に喩えれば、味噌を仕込んでから、それを米に混ぜて発酵させて濁り酒を造るような感じである。
.
.
マジョリティと少数民族が居合わせると、よく起きる現象なのだ。例えばミャンマー。シャン人とカチン人といった少数民族の人たちは、普段は自分たちの言葉を喋っていても、その場に多数派のビルマ族が一人でもいると全員が自動的に言葉を公用語のビルマ語に切り替える。トルコのクルド人の村人も同様で、その場に一人でもトルコ語を話す人がいると全員がクルド語を使わずトルコの公用語であるトルコ語で話す。
.
.
信じがたい事だが、7歳の子供が丸一日、ビールと同じくらいの度数の酒を500mm缶4~5本飲んでいるようなのだ。しかも他に何も食べないし、水も飲まないという。それを証明するかのようにインタビュー中も、この子は一人ですることもなく退屈なのか、ぐびぐびと酒を飲み続けていた。
.
.
誰も彼も酒を飲んでいる。パルショータは食事と水を兼ね備えたスーパードリンクなのだ。酒は煮炊きする必要がなく、一日、陽にさらされていても傷まない。好きなときに好きなだけ飲める。仕事中にはこれ以上便利な飲食物はない。
.
.
病院内を見学させてもらったのだが、私は驚きを通り越して笑ってしまった。なにしろ、入院している患者がみんな病室で酒を飲んでいるのだ。
.
.
「少なくともパルショータが健康に被害を与えていると示唆する兆候やデータはありません。子供の栄養失調が極めて少ないです。モリンガやブランゴ(エチオピアンケール)を食べていると、高血圧や糖尿病になりにくいんです。デラシャの飲酒には何の問題もありません」
.
.
デラシャの人たちは子どもの頃から酒を飲んでいると聞いていたが、それは正確な表現ではなかった。「生まれたときから」と院長は言っていたがそれも違う。ここの人たちは「生まれる前から飲んでいる」のだ。なぜなら、妊婦がアルコールを摂取すれば、血液を介して確実に胎児に伝わるからだ。
.
.
以上引用です
.
.
■
.
.
アフリカエチオピアの酒飲み族を探しに出かけたオデッセイ。
.
今回はTBSの番組クレイジージャーニーのスタッフと共同らしく、地上波でも放送されたのかも。見ていないので分からない。
.
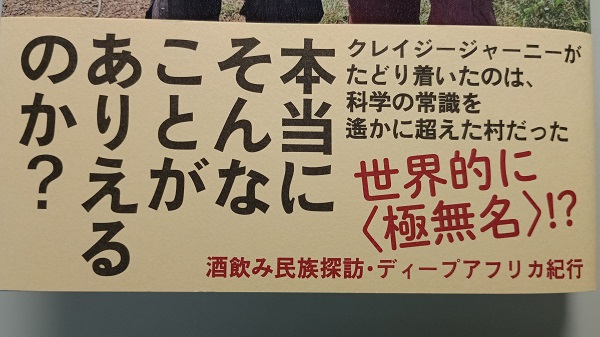
.
この人の素敵なところは、出来る限り現地の人に溶け込んでありのままの生活や体験を試みる姿勢だと思う。
.
にわかの虚栄心や好奇心ではなく、ホンモノへのあくなき探求心というか、現地の住人に最大限敬意を払いながら郷に従っている。
.


.
そういう経験に歴史的な経緯、文化や慣習を落とし込んで、今回も常識のパラダイムシフト見せつけてくれた。
.
現地の人が伝統的な佇まいを偽装していた件は、驚きを通り越して笑った(笑)
.
■
.
最後に印象に残ったところを
.
.
イスラム圏を長く歩いている私には、単純に酒を飲まない生活が健康にいいなどとは到底思えない。イスラム教徒の中には、酒の代わりに頭が痛くなるほど甘いお菓子を食べ、お茶を飲んでいるのか砂糖水を飲んでいるのかわからないようなチャイを一日に十杯以上も飲み、これでもかと油を入れた料理を食べている人が少なくない。私のイラクの友人は「イラク人は大体、高血圧と糖尿病で死ぬ」と言っている。
.
.
最低でも「酒が有害かどうか」などという単純すぎる議論はデラシャとパルショータを十全に研究してからにしてもらいたい。それが多様性時代のフェアで科学的な態度だろう。
.
.
現代の「高度に精製されたアルコール」との違いもあるのかも。
.
そしてもう一つだけ
.
.
私がイメージしたのはNHKの「ドキュメント72時間」である。ユニークなのは一発勝負であることだ。例えばコンビニを選ぶとき、いろいろなコンビニを撮影してその中の標準的なものを選ぶとか、何度も72時間撮影を行ってその中で一番面白いものを放映するということはしていない。ときには何も目を惹くことは起きないし、ときには異例な物語が展開する。たった三日間ではその場所の何が分かるわけではないけれど、でもそこで映っていることは間違いなく事実であり、その場所の真実を伝えている。
.
.
ぜひ読んでみて欲しいな。
.
.
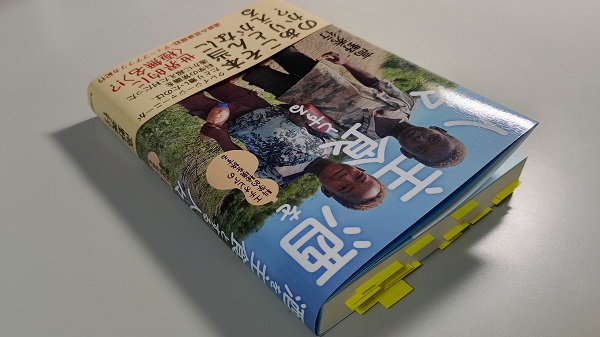




コメント