「嫉妬論」を読み終えた。
.
.
面白そうだったので購入。この人の本は初めて。
.
.
■
.
.
スイス東部にあるベルギューンはとても美しい観光地として知られているが、ベルギューンはそのあまりのインスタ映えのために、写真撮影を禁止した。街には以下のような看板が設置された。「絵のように美しい風景の写真をソーシャルメディアでシェアすると、他人を不幸にしてしまうかもしれません。なぜなら、彼らはここに来ることはできないのですから」撮影行為の禁止はもちろん茶番である。実際のところ #bergun で検索すると多くの写真がアップロードされており、むしろそれは注意書きがソーシャルメディアでバズることで休暇嫉妬をますます煽るプロモーションであることは明らかである。
.
.
インドのカーストのような社会では、復讐感情は醸成されにくく、ルサンチマンは大したものにならない。むしろ私たちのような社会のほうがルサンチマンは生じやすい。つまり、政治的その他の点において形式的に平等な権利が認められていながら、実際には極めて不平等な社会のことである。
.
.
喪の儀式で暗い服を身に纏い、快楽に結び付く様々な活動を自粛するのも、死者に生者を嫉妬させないための象徴的な行いであるという。
.
.
嫉妬とは「他人の幸福が自分の幸福を少しも損なうわけではないのに、他人の幸福を見るのに苦痛を伴う性癖」である。隣人の成功は私の状況とは差し当たり関係のないものであったとしても、私の幸福を曇らせ、私の不遇を際立たせる。さらに「嫉妬の活動は、人間の本性に属していて、それがいったん爆発すると、少なくとも願望としては他人の幸福を破壊せんとする、自己自身を苛む陰険な欲情といった忌まわしき欲情となる」(イマニュエル・カント)
.
.
憎しみはその対象である人物が悪い人間であることを必要とするが、妬みはただ幸福を目にするだけで生じる。また憎しみには限度があるが、妬みには限りがない。
.
.
私たちは、自分より優れた知識や技術を持つ者を最初は崇拝したり感嘆するであろう。しかし自分の技術が向上するにしたがい、今度は相手に嫉妬するようになる。そしてその嫉妬が自分自身をいっそう前進させる燃料にもなるのである(良性嫉妬)そして嫉妬者が嫉妬の対象と同等になったとき、その悪情感は静まり、相手が丁寧に接してくれると途端に仲良くなる。「思っていたよりいいやつだった」というわけだ。
.
.
優位者は最初、劣位者との比較から快楽を受け取るが、しかし劣位者の相対的な上昇は優位者の快楽を減じてしまうため、これを不快に感じるのである。だとすれと厳密には、優位者の比較の対象は劣位者というよりも、より大きな快楽を享受していたかつての自分自身ということになるだろう。
.
.
誇示者の欲望は単に財を享受するだけでは満足しない。むしろ財や優位性を他人に見せつけ、嫉妬されたとき初めて満たされるのだ。言い換えれば、欲望が満たされるには対象だけでなく、それをほぞを噛んで見つめる第三者が必要になるわけだ。
.
.
さらに不快に思われるのは、自慢話がともに賞賛するよう私たちに強いるからでもある。自慢話に閉口していると相手はこちらがやっかんでいると思うかもしれない。そうした嫌疑を逃れようとすれば、おのずと賞賛の輪に加わらざるをえないわけだが、これは「敬意による行いではなく、媚びへつらいであり奴隷的な行いであると言うのがふさわしい」(プルタルコス)と厳しく評価される。
.
.
同期に入社した同僚に比べて、自分の地位が低かったり給料が少なかったりしても、それが意地悪い上司の不当な査定のせいならば自尊心は保たれる。序列の基準が正当ではないと信ずるからこそ人間は劣等感に苛まれずに済む。公正な社会ほど恐ろしいものはない。社会秩序の原理が完全に透明化した社会は理想郷どころか、人間には住めない地獄の世界だ。
.
.
閉じた社会では人々の嫉妬心を強めるファクターのほうが作用する。たとえば目に見える不平等がなくなるほど、細かな差異が目につきやすくなる。人々が物理的に近く個人的な接触機会が多いことは、一度生じた嫉妬心をたえず意識することになるだろうし、個々人のバックグラウンドや受けた教育が同じであれば、自分が劣位の立場にあることを誰かのせいにしにくくなる。
.
.
嫉妬者が隣人の外見、若さ、子供、結婚の幸福などに我慢できるのは、他人の収入、家、旅行に嫉妬することによってみである。物質的要因が嫉妬に対する社会的に必要な障壁を形作っており、身体的な攻撃からその人物を保護している。
.
.
嫉妬のない社会とは、人々のあいだに差異のない完全に同質的な社会であるか、絶対的な差異のもとでいっさいの比較を許さない前近代的な社会であるかのいずれかであろう。そうすると嫉妬は私たちのデモクラシーの帰結ということになる。
.
.
平等を求める社会主義とは「他人より健康的な体、あるいは幸福な気質、うまく合った配偶者、または頼もしい子供を誰も持たないようにする」政治体制のことでしかないということになる。
.
.
民主主義が生き延びるためには、優越願望と対等願望のバランスが重要になる。民主主義の長期に渡る健全性と安定度は、優越願望が市民の役に立つような形での良質かつ多数のはけ口を持っているかどうかにかかっている。
.
.
嫉妬に何かしら意味があるとすれば、それはこの感情が「私は何者であるか」を教えてくれるからである。たいていの場合、私の嫉妬は他人には共感されない、私の嫉妬は私だけのものである。私は誰の何に嫉妬しているのか、なぜ彼や彼女に嫉妬してしまうのか。これは翻って私がどういう人間であるか、私は誰と自分を比べているのか、私はどんな準拠集団の中に自分を見出しているのかを教えてくれるだろう。
.
.
以上引用です
.
.
■
.
.
第二章の偉人たちによる嫉妬論がとてもよかった。どれも切れ味鋭く、特にイマニュエル・カントが腑に落ちた。
.
あと第五章の「嫉妬と民主主義」も大変興味深い。
.
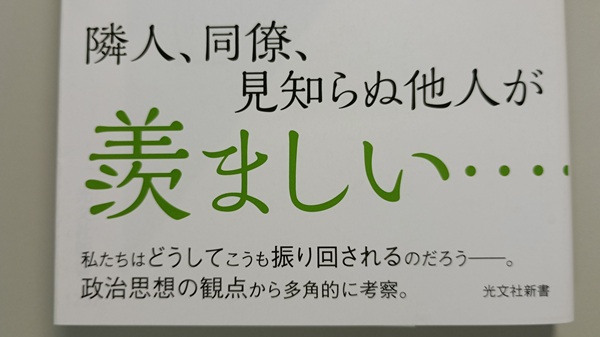
.
印象的だったのは、嫉妬が恐ろしいのは憧れや羨望と違い合理的な計算ができなくなってしまう。
.
.
嫉妬者は自分の損得に無関係に隣人の幸福を許すことができない。つまり彼(女)は自分の利得を最大化しようとしているわけではないのである。むしろ逆である。彼(女)はたとえ自分が損しようと隣人の不幸を願う。嫉妬は功利主義的な快楽計算には従わず、そうした自暴自棄さはある意味で、すがすがしく感じるほどだ。
.
.
もうひとつ、嫉妬は比較可能な者同士の間に生じる。
.
キャンセルカルチャーはあるにせよ、概してイーロン・マスクよりは似た属性の者を妬む傾向がある。
.

.
つまるところ、他人との間の優劣がかけ離れていることではなく、むしろ接近していることが妬みを生み出すと。
.
そうなると、格差が小さい社会はより嫉妬が蔓延るパラドックスに!?
.
格差の減少がますます嫉妬を搔き立て、不自由のレベルがカーストや北朝鮮クラスにならない限り嫉みは減少に転じない。
.
■
.
妬みは資本主義を突き動かす燃料だ。
.
そして健全な民主主義に欠かせないものでもある。
.
格差が縮んでも決して消滅しない厄介なものだからこそ、優越願望と対等願望のバランスが重要になるんだろう。
.
.
まとめると
.
嫉妬はしたくもされたくもない(できれば)
.
以上(笑)
.







.
最後に印象に残ったところを
.
.
誇示者もまた人々が等しく誇示するなかで、他人とは異なる真正さや独自性を求めてもがいている。しかし問題は、その欲望には決して真の満足が訪れないことである。「誇示の民主化」で万人が多かれ少なかれ誇示的に振る舞うことを可能にしたが、まさにそのことによって誇示そのものの条件が壊れてしまった。自慢が賞賛や嫉妬を必要とするならば、誇示の民主化のもとでその効用は著しく下がるだろう。まるで漂流する宇宙船から独りむなしくシグナルを送り続けるように、いまや時宜をまるで得ない、宛先不明の誇示だけが繰り返されている。これが我らの誇示者の成れの果てなのである。
.
農夫は善良な魔女からこう言われる。「なんでも望みを叶えてやろう。でも言っておくが、お前の隣人には同じことを二倍叶えてやるぞ」農夫は一瞬考えてから悪質そうな微笑を浮かべ魔女に言う。「おれの眼をひとつ取ってくれ」(スロベニアの物語)
.
妬みは休日をとらない(フランシス・ベーコン)
.
.
そしてこの本「絶対悲観主義」から、書き留めておいた名言を2つ。
.

.
「他人の幸福をうらやんではいけない。なぜならあなたは、彼の密かな悲しみを知らないのだから」ダンデミス
.
「誰でも友人の悩みには共感を寄せることができる。しかし、友人の成功に共感を寄せるには優れた資質が必要だ」オスカー・ワイルド
.
.
いい言葉だなー
.
.
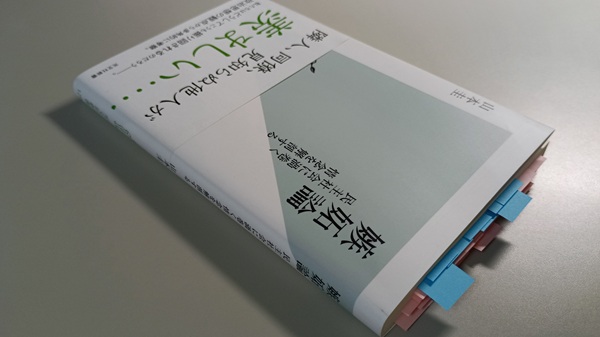




コメント